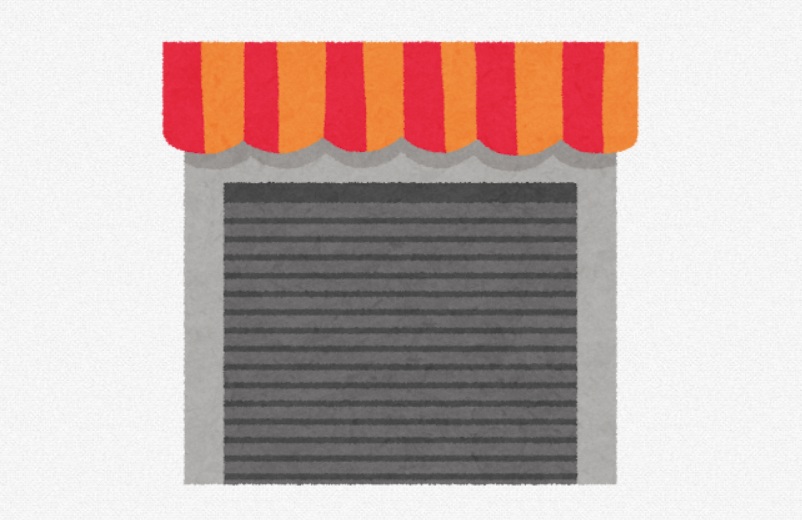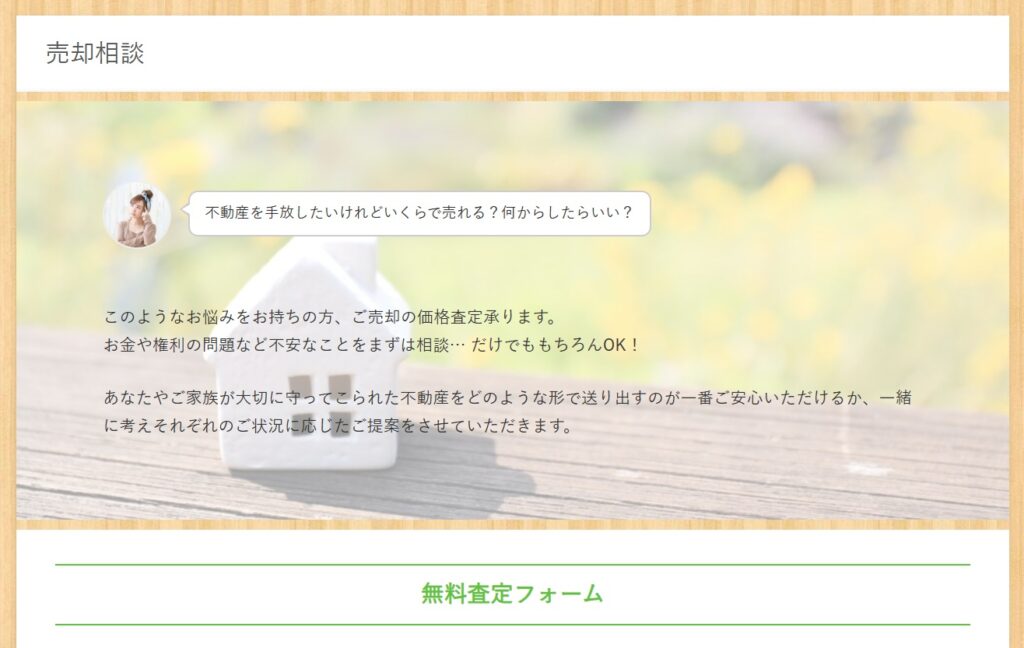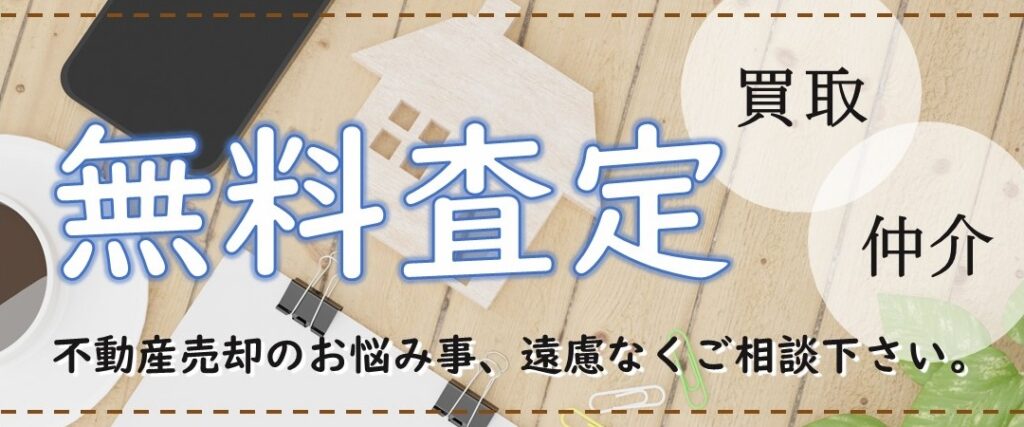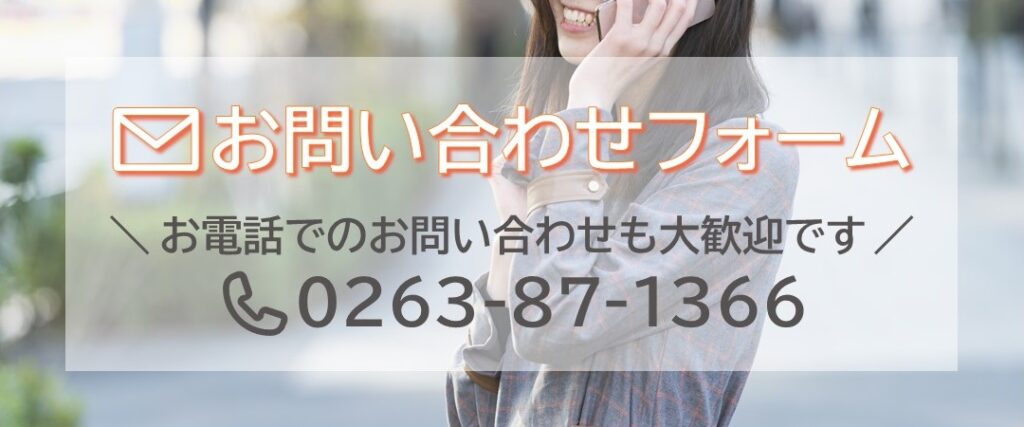土地の面積は権利証や法務局備付の登記簿謄本で確認することができます。地目が宅地になっていれば小数点以下2桁まで表記されていますので何となく信憑性がありますが、畑や田になっていると小数点以下の表記がされていないので、測量すると必ずと言っていいほど異なってきます。
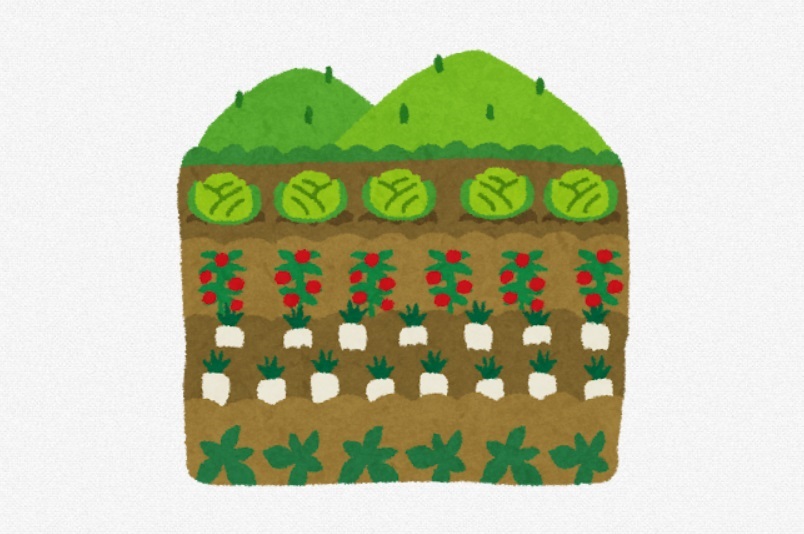
宅地になっていても、登記の日付が昭和や平成の初期になっていれば、あらためて測量すると高い確率で面積が異なります。平成17年頃までは土地を分筆した際に元の面積から差し引いて残った面積を算出していましたので、今の技術で測量すれば面積は増減する可能性が高いです。
多少の面積増減であれば、売却購入価格や建築計画に影響することは少ないとは思いますが、大きく変更となると売買そのものが成立しないことも考えられます。売買契約の多くは公簿(登記簿)面積で契約しますので、測量後の面積によって売買金額を精算する条項を設けることもあります。
お金の精算だけで済めばまだしも、希望していた間取りの家が建たないとなると目も当てられないので、見た目からどうも不安な場合や、そうでなくても念のため建築会社に簡易的に測量していただくと良いでしょう。簡易測量といってもかなり正確に算出していただけると思います。
弊社物件でも過去に、面積を測ってみたら登記簿面積よりも90㎡も異なっていたという事案がありました。90㎡と言えば場合によっては一軒家も建築できるほどの面積ですが、購入を検討していただいた建築会社さんに簡易測量していただいて発覚したものです。
昭和40年代の古い団地の一角の角地でした。当時は測量方法も簡易的で角地であったことから最後の方の残地だったのでしょう。さらに二方向の道路と接していたため民間地との調整が少なかったこともあり、残った残地面積をそのまま登記したものと考えられます。
情報公開前に登記簿面積で買い手がほぼ決まっていたものがキャンセルとなり、あらためて建築会社さんに提案した矢先の出来事でした。結果的には3区画計画を2区画計画にしてお申込みいただくことができましたが、弊社としての販売計画は大幅に狂う結果となってしまいました。
平成17年以降の測量図が備えられた宅地であればそれほど面積の増減の心配はないですが、古い記録の田畑などは簡易測量をする、さらに売買契約書には測量後の代金精算や希望の建物が建築できない場合は解除するといった特約条項を個別に盛り込むケースもあるかもしれませんね。



![[物件情報] 松本市梓川梓の中古住宅を追加しました](https://hic-fudousan.com/wp-content/uploads/2026/01/azusagawaazusabs1-300x225.jpg)